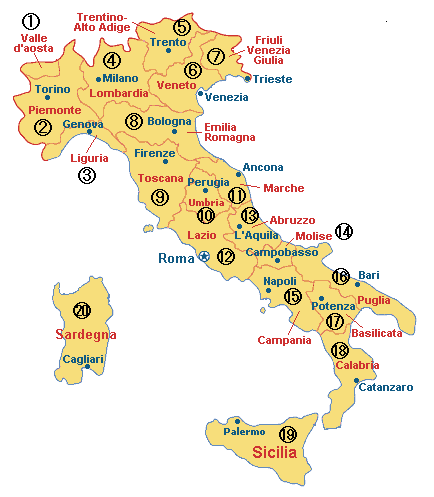ハーブ系リキュール
ヨーロッパ各地で愛飲され続けてきた薬草(ハーブ)系のリキュールは、一部の銘柄を除くと日本では馴染みではありません。ジン、カンパリ、クレム・ド・ミント以外となると、せいぜいシャトリューズ、ドランビュイ、ヴェネディクティン、ペルノーくらいではないでしょうか?苦味が強めの銘柄が多く、嗜好品としてより滋養強壮酒として発展してきました。蒸留酒の歴史において需要な役割を果たし、本来は本筋とも言えますが、甘美追求型のカクテル用リキュールに押されて、日陰に追いやられてしまいました。地域性が強い事もあり、日本では知名度の低い銘柄がほとんどです。何世紀のも間ヨーロッパの各地で飲まれ続け、愛され続けてきた味わい深い各種の銘柄を紹介したいと思います。数多くの中から長年の洗練と選択を経て生き残った銘柄たちは、新鮮な驚きと新しい味の発見を与えてくれます。
(精細については、銘柄名をクリックして下さい。★印は低アルコールの銘柄です・お酒が弱い方もお楽しみ頂けます。)
イエイガーマイスター (ドイツ/バランスのとれた入門銘柄・とりあえずお勧め)
ドランヴュイ (スコットランド/この地域ならではの甘めながら上品でドライな味わい)
ストーン・ジンジャー・ワイン ★ (ブリテン/馴染みやすくてお勧め・軽やかです)
ピムスNO1 (ブリテン/甘ホロ苦い伝統のリキュールカクテル)
ピコン・クラブ ★ (フランス/オレンジ風味で親しみ易いエキゾティック味)
ウニクム (ハンガリー/濃〜い味の超クセ者)
フリゴラ (スペイン/タイムがかもし出すチルアウトな楽園味)
<イタリア>
カンパリ (お馴染みのイタリアンビター代表)
アベロール ★ (優しくユルいオレンジ風味・カンパリ系)
チナール ★ (ドン臭さが魅力の田舎娘?カンパリ系)
アヴェルナ・アマーロ (シチリアの伊達男?カンパリ系)
フェルネ・プレソラーナ (奥深く複雑な苦味!素晴らしいです)
ポーリ・アマーロ (苦味一本勝負!糖分ゼロ・・)
ポーリ・アペリティフ ★ (ベリーと唐辛子で新鮮な味わい)
コカ・ブトン (終売品、激甘、コカの葉・・・・)
ラ・イタリアーノ (絶品アブサン、イタリアより登場!)
(カンパリ系と表記してある銘柄がありますが、別にマネっこと云う訳ではありません。イタリアン・ビター酒は昔から各地にありましたが、大まかながら味の傾向には共通点がありました。その中で世界的に有名になったのが“カンパリ”だったので、分かり易くカンパリ系としました。という訳で、それぞれ違いを楽しんで頂ければと思います。ハーブリキュールなので、スコッチや焼酎などより味の違いは大きいんですよ。)
イェーガーマイスター ( Jagermeister ) < ドイツ > ミント、リンドウ、アニス、甘草、蜂蜜、など (40度)
・日本でも比較的ポピュラーな銘柄なのは、苦味が少なめながらも甘味とのバランスも良く、入手もし易いからでしょう。本国では、ビールの友として傍らに置き、胃が冷えてきたなと思ったら小さなグラスでクイッとやるようです。
・複雑ながら親しみやすい味わいで、美味しい!ハーブリキュール入門銘柄としてお勧めします。
・ストレート、ロック、ソーダ、トニック、ジンジャエール、オレンジなど飲み方を選びません。
・ 56種類ものハーブ、果物、植物の根、スパイス、フルーツ を使っていると言われていますが、公表されていません。かつて、鹿の血やアヘンが入っているとの噂を呼んだのも、銘柄の持つイメージや独特の味わいからの妄想が膨らみすぎたからでしょう。1935年の発売と、比較的新しい銘柄ですが、カンパリにつぐ世界代2位の売り上げを誇る人気リキュールです。
・ドイツ語で“ハンターの守護聖人”の意。7,8世紀頃のドイツの逸話で、牡鹿の角に精霊をみた人物が後に聖職者の道を選んだと言う物語が其の名の由来だそうで、ゲルマン民族の森林崇拝を思い起こさせる神秘的でシャーマニックなイメージの飲み物です。当店の入り口の下り階段突き当たりに掛けてある鏡がイェーガーマイスターのパブミラーで、聖なる鹿君が悪霊の侵入を防いでくれています。

1994年のDTMでアルファにスポンサード
ドランビュイ < スコットランド(スカイ島) > ・ヒースの蜂蜜など / ハイランド・モルト・ウイスキー (40度)
・15年以上熟成のハイランド・モルトを中心に40種ほどのスコッチとヒース(エリカ)の蜂蜜、ハーブ、スパイスなどをブレンド。
・ウィスキー味の力強く深甘いリキュールです。
・ロック、ソーダ、トニック、オレンジなどで・・スコッチとミックスしたラスティ・ネールというカクテルが有名です。
・1745年、イギリス王位を争っていたチャールズ3世が、戦いに敗れ、30000ポンドもの賞金を掛けられた後スコットランドへの逃避行を余儀なくされました。彼を庇護しフランスへの逃亡を助けたハイランドの士を代表して、ジョン・マッキノンに褒美として王家秘伝の酒の製法が授けられます。 以後マッキノン家の秘蔵酒として150年間ほど門外不出でしたが、1906年に販売が開始さました。ボトルに"Prince Charles Edward's Liqueur"と記されています。「ポニー・プリンス・チャーリー」の愛称で親しまれた彼は、今でもスコットランドのアイドルです。
・この、伝統的リキュールを味わう度に、当時の人々の甘味という得がたかったであろう快楽への嗜好性を感じる事ができます。当時、甘味料がクスリ的役割を果たしていたという経緯もあり、甘くて美味しくて元気になる「満足できる酒」でした。ドランブイ(Drambuie)の名は「満足できる酒(dram buidheach)」というゲール語に由来しています。
・この地のヒース(ヘザー)から採れる蜂蜜は「スコティシュ・ヘザー・ハニー」と呼ばれる特別品で、ワインの様な熟成を経て○○年物的なビンテージ扱いをされている様です。スコッチ・ウイスキーの香味にも「ヘザー・ハニーの様な・・」と表現される要素があり、ウイスキーと蜂蜜の出会いは地域的必然とも言えるようで、他にも幾つかの同種銘柄があります。アソール・ブロス、ロッカン・オラ、ケルティック・クロッシング アイリッシュ・ミスト、などです。
 |
|
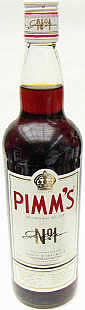 |
|
|
 |
|
 |
|
・(そんな細かい事どうでもいいヨ・・と思われるんでしょうが)イピザとの表記が多いんですけど、島民の発音通りのイピサと表記しました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
イタリアのハーブリキュール!
・さて、ハーブ系苦味リキュールの激戦区と言えばイタリアです。生まれ故郷に対する狂信的偏愛を持つイタリアの人々は「イタリア人なる者はいない」と云われる事も多く、国が一つになるのはサッカーの国際試合の時だけらしいです。この意識は食文化にも強く反映していて、「イタリア料理と言うものは無く、各地方の料理が存在するだけ」だそうです。リキュールも類似の味わいを持ちつつも、地域銘柄が各自の味覚根拠と存在感で愛飲されています。ストレートで飲むと似た感じでも、ソーダなどで割ると個性の違いが明白に浮かび上がります。
(★印は低アルコールの銘柄です・お酒が弱い方もお楽しみ頂けます)
カンパリ <イタリア北西部/ピエモンテ州> 60種のハーブ (32度)
・1860年、ピエモンテ州トリノのバーテン、ガスパーレ・カンパリ氏が自分のレシピで発売しました。その鮮やかな赤い色(今は着色料ですけど)とバランスの取れた味わい、甘味全盛の時代に切り込んだ販売戦略と運も味方して、今や世界で随一の普及率を誇る苦味ハーブ系リキュールです。
・さすがにコノ味は説明無用?ロック、ソーダ、トニック、コーラ、ビール、と何でもござれの融通性。スプモーニも有名ですが、冬のお湯割りが意外とイケる・・
・1860年に発売された時は、当時の流行?に乗って「ビッテル・アルーソ・ドランディア」(オランダ風苦味酒)と名付けて売り出したそうです。商売人ですね・・でも、何の流行だったんでしょうか?
・カンパリの突出度はスゴイです。各地域の伝統酒として小規模生産されていた田舎の苦味リキュールを、「都会的(トリノはイタリア第四の都市です)センスで洗練させ普遍性(生産性や流用性)を持たす事に最初に成功したのみならず、積極的にマーケットにアプローチした」と見るのが妥当かもしれません。先鞭をつけた物が市場の主導権を握るという点で、サンタフェ研究所の「複雑系経済学」が指摘する不完全合理性の好例かも知れません。
・上記に人工着色料の使用について書きましたが、以前は 虫から採取した色素で赤く色付けていたんです! 長らくメキシコのエンジムシ(ウチワサボテンに寄生するカイガラムシ)のコチニールなるカルミン酸色素が使用されていたとの事・・この虫はアステカやインカ帝国などで古くから養殖されて染色用の染料に使われてきたそうです。
・この事を知ったら虫嫌いの人は飲みたくなくなるに違いないですね・・絶対的な企業秘密じゃないですか?後述のアルケルメスというリキュールにも使われています。
 |
|
 |
|
・カルティーフイはアーティチョークや朝鮮アザミなどと呼ばれる、西洋ではポピュラーな地中海原産の野菜です。イタリア中部から南、サルデーニャ島やシチリア島が有名な産地。日本では栽培条件が合わず、三浦半島などで少量作られている程度で、ヨーロッパと違いかなりの高級食材になっています。海外の料理本では頻繁に見かけるので憧れてる人も多いのでは?(私もです・・・)
 |
|
・シチリアと言えばマフィアですが語源が面白いです。1282年に起きたフランスへの反乱の合言葉が 「全てのフ ランス人に死を、これはイタリアの叫びだ!」でした。イタリア語だと「Morte alla Francia Italia anela!」で、頭文字を並べれば <mafia>となります。これが由来という説が有力だそうでが、シチリアマフィアは自らをマフィアとは呼ばず、 コーサ・ノストラ(La Cosa Nostra)「我々のもの」と呼んでいるのはご存知の通りです。ちなみに、「 ピッツォ(シャバ代)」などを含むシチリア島マフィアの違法収入は毎年10億ユーロ(約1600億円)に達すると見られており、同島の総生産の1.3%に当たるそうです。
 |
|
^  |
|
 |
|
 |
|
・上記にある通りロスト・ラベル(終売)の半ヴィンテージ品です。度数が比較的高いので大丈夫だと思いますが、味が劣化しているかもしれません。逆に瓶内熟成している可能性も期待できます。ご了承の上で御注文下さい。
・イタリアはハーブ酒王国なので、19世紀末のアブサンブームには動じませんでした。しかし、北イタリアは地域的にアブサン震源地と同じエリアにあり、近年ではアブサンの生産も行われています。特に下の銘柄の本気度は高く、ハーブ酒王国の面目を掛けてアブサンに挑戦しています。アブサン評価サイトでは高評価を勝ち取り、新鋭の銘柄として注目を浴びています。(アブサンについてはこちらとこちら)
 |
・“L'Italienne”はイギリスの酒類流通業者 <LdF>のプロデュ−スで実現した特別なアブサンです。地産ハーブ(※)にこだわり、その選択と品質には今までに無い細心の配慮がなされました。使われている高品質のピエモンテ産ニガヨモギは長年イタリア産ヴェルモットの評判を支え続け、一朝一夕に出来たものではありません。他の主要ハーブもエミリア=ロマーニャ州の契約農家の有機栽培品を軸に、イタリア中から集められたそうです。もちろん高品質のグレープスピリッツの使用も必須条件でした。そして、その味わいは「the feminine and floral style absinthes 」との事で、かつてのPernod et Fils社製アブサンに冠された形容詞を標榜する事は、アブサンの理想形を現出せしめんとの心意気を表しています。イタリアというアブサン業界では評価されずらい国から、丁重で確信犯的な企たくらみが届きました。女性的な繊細さと華やかな花の香りを放つイタリアの名花をお試し下さい。(65度) ・ハーブリキュール王国ともいえるイタリアでは同種のハーブ酒は既に普及しきった末に嗜好性が確立しており、アブサンの需要・生産は全盛期においても盛んではありませんでした。しか、しグラッパにも反映された独自の歴史を誇る蒸留技術やハーブ類の扱いの熟達度などには他国を凌駕する側面を持ちます。新時代を向かえて幾つかのイタリアン・アブサン銘柄も登場しはじめた矢先に、アブサン最大指針国のイギリスから打ち出された華麗なる巨大砲弾(ボトルも太い)です。
|
(※)例えば、ポンタリオやボバレスの様な本場と言えども全ての原材料が地産というわけではありません。昔から<聖なる三草>の内、フェンネルはイタリアや南フランス、グリーンアニスはスペインや南フランスなどの地中海沿岸産が使われてきました(参照)。そして、適正生育主要ハーブ(ニガヨモギ、小ニガヨモギ、メリッサ、ヒソップス)ですら禁制期には栽培が途絶えており、密造者達の多くは自生ハーブを使用していたそうです。規制解除直後は、商品化に必要な量と品質を確保可能な栽培技術が必要で、その試行・検証には大きな苦労があったようです。(参照)
・栽培法のみならずハーブを良い状態に乾燥させる技術も以外に難しいようで、原材料の品質管理において重要なポイントになるそうです。適正な収穫時期とか含有水分量など酒用以外の用途とは異なる要素が求められるのではないでしょうか?ハーブリキュール王国のイタリアがこの点でも突出しているであろう事は容易に推測できます。
左は使い物にならない×メリッサ 
 右はップ・クォリティーの◎メリッサ
右はップ・クォリティーの◎メリッサ
イタリア北西部
1. ヴァッレ・ダオスタ州 (アオスタ)
2. ピエモンテ州 (トリノ)
3. リグーリア州 (ジェノバ)
4. ロンバルディア州 (ミラノ)
イタリア北東部
5. トレンティーノ・アルト・アディジェ州 (トレント)
6. ヴェネト州 (ベニス)
7. フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア州(トリエステ)
8. エミリア・ロマーニャ州 (ボローニャ)
イタリア中部
9. トスカーナ州 (フィレンツェ)
10. ウンブリア州 (ペルージャ)
11. マルケ州 (アンコーナ)
12. ラツィオ州 (ローマ)
イタリア南部
13. アブルッツォ州(ラクイラ)
14. モリーゼ州(カンポバッソ)
15. カンパーニャ州 (ナポリ)
16. プーリア州 (バーリ)
17. バジリカタ州 (ポテンツァ)
18. カラブリア州 (カタンツァーロ)
イタリア離島部
19. シチリア州 (パレルモ)
20. サルデーニャ州 (カリアリ)
以下の銘柄は未入荷です。
アルケルメス |
|
イタリア中部/トスカーナ州 |
|
|
|
南洋諸島産の香辛料、花の抽出液など |
|
・ イタリアのトスカーナ地方、フィレンツェの有名なサンタ・マリア・ノヴェッラ教会付属の薬局で1743年に生まれました。 ・ お菓子好きなら知っているズッパ・イングレーゼの味付け&色付けの為に使われるお酒。 とっても甘くて、そして喉がかぁぁーっと熱くなります。最初にシナモンとクローブの香りが来ますが、すぐに花の香りに変わります。独特の 深みと香りと余韻 。スパイシーな香水を飲んでるみたい・・ |
|
・カンパリの項で触れたエンジムシを使って、鮮やかな赤い色を出しています。

・フィレンツェのお菓子「ズッパ・イングレーゼ」について現地に住む方のブログから引用してみました。「アルケルメスと、お好みのリキュールをしみこませたスポンジに、カスタードと生クリームを重ねて冷やせば出来上がりです。リキュール類の量はお好みで変えればいいと思うのですが、アルケルメスは、スパイスとバニラの香りがするので、スポンジがかなりひたひたになる位に漬けた方が、カスタードクリームのバニラ香とマッチしておいしいように思います。」ですって、美味しそうですね・・・
 |
ストレガ |
イタリア南部/カンパーニャ州 |
|
40度 |
|
サフラン、アニス、フェンネル、ミント、レモン果皮など |
|
・イタリア語で“魔女”という意味の名を持つこのリキュールは、サフランの黄金色に輝く香り高い名品です。イタリア南部のヴェネヴェント市で 1860年に誕生しました。 ・ ハーブの香りとバニラ風味の爽やかさかさと、オーク樽による長期間熟成の深みが調和した、繊細で品のある洗練された味。“輝く太陽の溶液”と称される、南部を代表するリキュールです。 |
|
・上記のほかに、シナモン、フィレンツェ・アイリス、ジャマイカ・ペッパー、アペニン山脈のエニシダ、サニオ、イリス・ペパーミント・エニシダ など、 ヨーロッパ、中央アメリカ、アジア諸国からの70種類以上ものハーブ、天然香料、スパイスを使用しているそうです。
|
|
|
|
| ・ | |
|
|
|
|
| ・ | |
|
|
|
|
| ・ | |